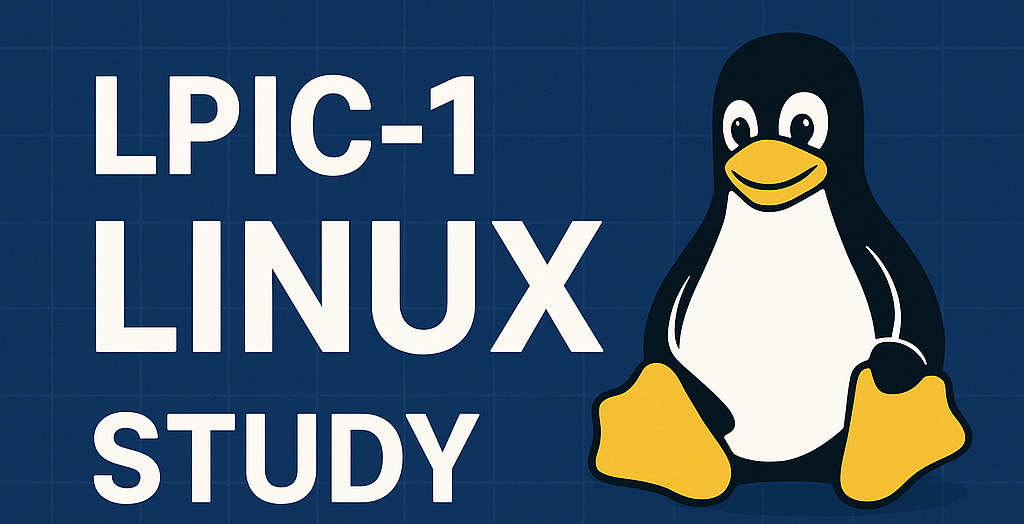1.OSとは
「OS」はコンピュータ管理や、ユーザの操作環境を提供する基本ソフトウェアのこと。このOSの一種としてLinuxがある。OSは、下記のような機能を提供する。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| ハードウェア制御 | CPU・メモリ・ディスク・ネットワークなどの管理 |
| ユーザーインターフェース | 画面表示や入力受付(GUIやCUIなど) |
| ファイル管理 | ファイルやフォルダの作成・保存・読み込みなど |
| アプリ実行管理 | アプリの起動・終了、メモリやCPU使用の管理 |
| セキュリティ | ユーザーごとのアクセス制御、権限管理など |
2.OSの構成
OSは主に「カーネル」「デバイスドライバ」「ライブラリ」の3つで構成されている。
※本当はもっと多いですがlpic1の範囲で掲載します。
- カーネル…ハードウェアと直接やり取りし、CPUやメモリ、デバイスなどを制御。
- デバイスドライバ…コンピュータに接続されたデバイスの管理・操作をするもの。
- ライブラリ…小さいプログラムの集合で、OSの機能を簡単に利用できるようにしたコード。
3.LinuxOSの種類
Linuxはもともとカーネル単体を指すものであったが、現在はディストリビューション(便利なソフトウェア等をカーネルに合わせてパッケージにしたもの)のことを指して使われることが多い。本サイトでもディストリビューションを指すこととする。
LinuxはOSS(オープンソースソフトウェア)であり自由に改変や再配布ができるため、開発方針等により様々なディストリビューションに派生した。
現在は大きく3系統に分かれており、それぞれ付随するソフトウェア等が異なる。
- Red Hat Enterprise Linux
- Slackware
- Debian
なお、LPIC1では、RedHatとDebianが出題範囲になっている。
※管理人はRedHatの中のCentOSを使っています。RedHatは有償で保守を行ってくれるため、仕事でも利用することが多く個人的におすすめです。
4.Linuxが使われる場面
Linuxは主にサーバ側のOSとして使われる。
サーバとは、利用者(クライアント)からのリクエストを受けて、それに応じたサービスを提供するものを指し、リクエストに対して応答することをレスポンスと言う。また、利用者側とサービス提供者を分ける運用をクライアントサーバシステムと言う。
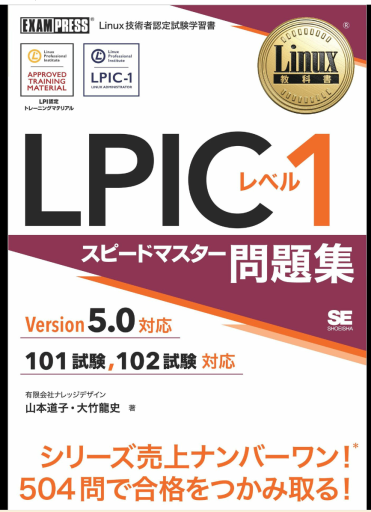
![徹底攻略 LPIC レベル1教科書&問題集[Version 5.0]対応](https://at-eichi-labo.com/wp-content/uploads/2025/10/495e9376d31fac1065679c6147c2a975-e1761222027471.png)